一般内科の診療
咳、発熱、頭痛、インフルエンザ、肺炎、糖尿病、生活習慣関連(高血圧、高脂血症、肥満等)、貧血、喘息、肺気腫、不整脈、動脈硬化など内科一般の診察を行います。
内科・胃腸内科
INTERNAL MEDICINE /
GASTROINTESTINAL
咳、発熱、頭痛、インフルエンザ、肺炎、糖尿病、生活習慣関連(高血圧、高脂血症、肥満等)、貧血、喘息、肺気腫、不整脈、動脈硬化など内科一般の診察を行います。

血圧が高い状態が続くことで血管の壁に圧力が掛り、その結果、血管を傷めて次第に血管が硬くなり動脈硬化へとつながります。
高血圧の原因は特定されていませんが、遺伝的要因と食生活(塩分の高い食事)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、または運動不足や精神的なストレスなどの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。

血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が多い為に引き起こされる疾患です。
これらの余分な脂質は、動脈の壁にくっついて血管を硬く狭くしていずれ動脈硬化を引き起こします。
コレステロールには善玉コレステロール(HDL)と悪玉コレステロール(LDL)があり、善玉コレステロールは細胞内や血管内の余分な脂質を肝臓に戻す働きがある為、悪玉コレステロールを減らすことに役立っています。
高脂血症の主な原因は食生活(カロリー過多)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、運動不足、遺伝などが考えられます。

血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなる病気です。
人体は、たくさんの細胞から成り立っていますが、この細胞が働く為のエネルギー源がブドウ糖です。
膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが、血液中のブドウ糖を細胞の中に取り入れる役割を果たしています。しかし、このインスリンの量が不足したり、働きが悪くなったりすると、ブドウ糖が細胞内に取り込まれなくなり、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が高くなってしまうのです。
血糖が高いということは、体の細胞にエネルギーであるブドウ糖が十分に補給されず、そのため全身の細胞の働きが悪くなります。のどが渇く、尿が多い、傷が治りにくい、感染症にかかりやすい、疲れやすい、集中できないなどの症状が表れます。

鼻や喉に感染がおこり炎症を起こします。症状は、咳、鼻水、鼻づまり、軽いのどの痛みや発熱等で原因の9割以上がウイルスによるものです。
また、しっかり治さないとその後、気管支炎や肺炎に進行する場合もありますので、治ったと思って無理をせず、しっかり完治するまで来院されることをおすすめします。熱を含めた症状の経過をしっかり観察することが大切です。
インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。
インフルエンザに感染すると、1~5日の潜伏期間の後、38℃以上の高熱や筋肉痛などの全身症状が現れます。風邪よりも急激に発症し、症状が重いことが特徴です。
健康な人であれば、その症状が3~7日間続いた後、治癒に向かいます。気管支炎や肺炎などの合併症を発症しやすく、重症化すると脳炎や心不全になる場合もあります。インフルエンザウイルスには強力な感染力があり、いったん流行すると、年齢や性別を問わず、多くの人に短期間で感染が広がります。二次感染、合併症の予防のために、できるだけ早く受診することが大切です。
甲状腺は、いわゆる「喉ぼとけ」(甲状腺軟骨先端)のすぐ下にある、重さ10~20g程度の小さな臓器で、全身の新陳代謝や成長の促進にかかわるホルモン(甲状腺ホルモン)を分泌しています。蝶が羽根を広げたような形をしていて、右葉と左葉からなり、気管を取り囲むように位置しています。
甲状腺の疾患は、女性に多く見られます。ある調査では、健康と思われる40歳以上の成人女性を対象とした健診において、20%程度の高い頻度でなんらかの甲状腺疾患が見つかったという報告があります。
もちろん男性も甲状腺の病気にはなり得るのですが、圧倒的に女性のほうが多く発症します。
睡眠中に何度も呼吸が停止(1時間あたり10秒以上の呼吸停止が5回以上ある)してしまう、あるいは低呼吸状態(1時間あたり10秒以上、呼吸が50%以下に低下する)にあるという場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)と診断されることがあります。このような呼吸の抑制状態が続くと眠りは浅くなり、熟睡感が得られにくくなります。そして睡眠をしっかりとっているにも関わらず、日中など活動時において強い眠気に襲われるようになるなど、様々な症状がみられるようになります。
以下に該当する方は睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
特に運転業務や機械操縦業務の方は対応が急がれます。
また高血圧や心疾患、糖尿病の原因や悪化因子とも言われています。
患者様に認められる症状や訴えなどからSASが疑われる場合は、診断をつけるための検査を行います。簡易型検査装置を用いたスクリーニング検査で、同装置にある手の指や鼻の下に付けるセンサーを装着して睡眠をとっていただき、いびきや呼吸の状態を確認します。それによってSASか否かを判定します。使い方は簡単で、ご自宅で行っていただけます。検査の結果、睡眠時無呼吸症候群との診断を受けたら治療の開始となります。
なお当院は、主に中等症以上の方に対して、CPAP療法(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)による治療を行っています。これは、専用の鼻マスクを睡眠時に装着することで、鼻マスクの装置からある一定の圧力を気道にかけられる空気を送り込むことができる装置です。これを使用することで、閉塞されていた気道は押し広げられるようになります。その結果、呼吸困難となっていた状態は解消され、中途覚醒や不眠に悩まされなくなるだけでなく、鼻呼吸による睡眠が可能となって、いびきも出なくなるようになります。
また、軽症の方には、マウスピースの使用によっていびきの解消や気道閉塞の改善が認められることがありますので、歯科への紹介を行っています。
なおCPAP療法での治療期間中は、体調変化や治療状況などを医師に報告する必要がありますので、定期的に通院をしていただきます。その際に装置による違和感などがあれば、その都度ご相談ください。
胃腸内科では、胃腸の病気の他、胆嚢・胆管・膵臓の病気、肝臓の病気に対して専門的な診療を行います。
上記の症状がある方はすぐにご相談ください。
空腹時や朝方に腹痛や胸やけの症状が出やすい方は、逆流性食道炎の可能性があります。
急性膵炎とは、膵臓の急性炎症です。膵臓は胃の裏側にある臓器で背中側に位置するため、急性膵炎は上腹部の痛みと合わせて背中に強い痛みを感じます。
繰り返す慢性的な炎症によって、胃や十二指腸の粘膜が傷付けられ欠損する疾患です。傷が浅いうちは「びらん」とよばれ、やがて傷が深くなると「潰瘍」と呼ばれます。
腹痛をはじめ、胃痛・みぞおちの痛み・消化管の出血によるタール便(黒い便)などの症状がみられます。
虫垂に炎症が起きる病気で、時間の経過とともに症状が変わるという特徴があります。はじめはみぞおちの痛み、食欲不振や吐き気などの症状がみられ、やがて痛みの場所は右下腹部へと移動します。同時に腹膜炎を発症すると、高熱を伴います。
尿路結石は、尿中のカルシウムや燐酸、シュウ酸、尿酸などが固まって石になるものです。
尿管に結石がつまると、背中からわき腹あたりにかけて激しい痛みを引き起こし、あまりの痛みに吐き気や嘔吐の症状を引き起こす方もいらっしゃいます。
微生物(ウイルス)による感染によって起こる胃腸炎です。腹痛をはじめ、下痢、嘔吐、発熱などを引き起こします。危険因子となるウイルスには、ノロウイルス、ロタウイルス、カンピロバクターなどが挙げられます。
おなかの張りなどの便通異常が慢性的に(3か月以上)続いている場合、過敏性腸症候群が疑われます。多くの場合は、下痢から便秘の症状を繰り返します。
膀胱は腎臓から送られてくる尿を、一時的に溜める働きがあります。膀胱に細菌が繁殖してしまうと、腹痛の症状や、排尿時のトラブル(痛み、頻尿、尿意切迫など)の症状が見られます。
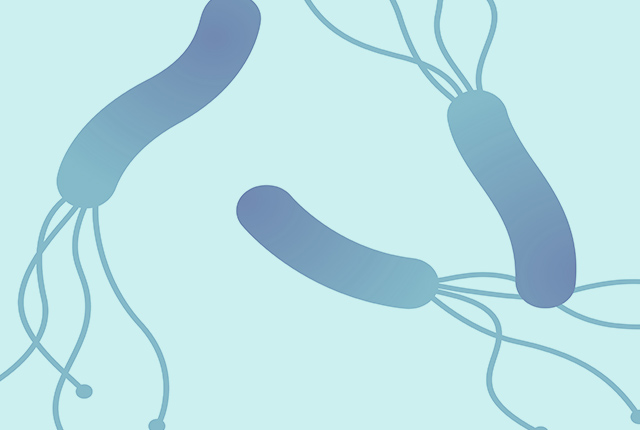
ピロリ菌は胃の中を好んで住み着き、胃の壁を傷つける細菌です。
主に幼少期に感染し、感染経路は「衛生環境」が疑われていますが、はっきりとはしていません。感染したからといって、潰瘍や胃がんが必ず発症するわけではありません。
しかし、感染したほとんどの人に胃炎が起こります。慢性的な胃炎(ヘリコバクターピロリ感染胃炎)になると、環境因子(ストレス、塩分が多い食事、発がん物質など)の攻撃を受けやすくなり、潰瘍や胃がんを起こしやすい下地を作ってしまいます。

カメラの管が太くライトも明るいので病変部分をより鮮明に見られます。
